何が起きているのでしょうか?
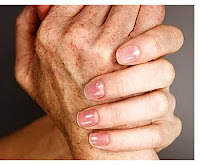 胃腸薬が、例えば鉄分の吸収を悪くするることは、知ってますよね。
胃腸薬が、例えば鉄分の吸収を悪くするることは、知ってますよね。しかし、
胃がチクチクするとき、胸やけらしいとき、
食べものに心当たりがなければ、心配です。
数日間は様子をみる、消えることもあり、続くこともある。
さすがに、一週間も続くと病院です。
将来のことですが、
高齢になっていくと、様々な不調に対処する薬剤も多くなりがちで、この薬剤の副作用で食欲が低下し、体力を無くしていくようです。
ちょっと調べると怖くなってくるのですが、
現状、本人にはあまり知らされていないようですね。
そもそも、
胃腸は、知らないうちに少しづつ、調子が悪くなっていくなんてことが あるのだろうか?
胃は老化するのか?
- 老化によって粘膜が萎縮、胃酸分泌が低下し、病原体への抵抗力が低下、吸収能力も落ちてしまう。
- 小腸では消化液を分泌する能力が低下、消化吸収が悪くなる。脂っこいものや、牛乳が飲めなくなったりする。
- 大腸では身体運動の低下によって便秘がちになる。
- 大腸壁の一部が小さな袋状に腸外に突出して憩室(けいしつ)を作り、感染を起こすこともある。
- 肝臓は老化の影響は受けにくいが、栄養素処理能力の低下やたんぱく質合成機能の低下がみられる。
- 肝臓のアルコールを処理する能力が落ちる。
- 歯が弱くなり、噛む能力が落ちる。
- だ液の減少などで口の中の衛生状態が悪くなる。
||||||||||
高齢者は若年者に比べて
食欲が低下している場合が多くなるという。
なぜか? 何が起きている?● 若いときに比べると心臓や呼吸器の能力が衰える。
● 骨や関節に障害が生じて運動が少なくなる。
結果、筋肉が萎縮し、一方で脂肪の蓄積が増え、同じ体重でも脂肪の割合が高くなっていく。
● 筋肉はエネルギー消費がきわめて高いのだが、
脂肪組織はエネルギーをほとんど使わない。
▼
からだが消費するエネルギー量が少なくなり、
食事からエネルギーをたくさん摂らなくてもよくなる。
加えて、身体的能力の低下や、その治療から胃腸への影響がある。
味覚や嗅覚、視覚も食欲に影響している
味覚や嗅覚も食欲に大きな影響を与えます。
これらの機能が低下して、料理の味や香りを楽しめなくなれば、当然食欲も進まなくなります。
老人性の白内障は程度の差はあれ、ほとんどの高齢者にみられます。水晶体が黄色く濁ると、見るものすべてが黄色味がかって見えます。鮮やかな配色の料理の盛りつけも、若い人ほどは食欲につながらないでしょう。
疾患による直接の食欲低下、利用薬剤による副作用
うつ状態にある高齢者の割合は高いと言われ、気力が失せ、あるいは生きる希望がなくなれば食欲も落ちる。
- 心不全や慢性気管支炎などの病気では、体力が消耗し食欲も低下する場合が多い。
- 心不全の時に使われる強心剤などには食欲を低下させる作用を持つ薬剤もある。
- 高齢者に多いリウマチや腰痛症などは、使われる痛み止めが胃腸障害の原因。
- 味覚障害は食欲を無くす原因になるが、降圧剤や脂質異常症(高脂血症)治療薬などの副作用や、骨粗鬆症の予防、治療ためのカルシウム製剤の取り過ぎなどで亜鉛欠乏症になり、副作用で障害となっていることがある。
普通、みなの思いは同じですが、
歳を重ねると、腰やヒザの傷み、目の病気、眠れない、若いときには想像できない不調が現れてきます。病院に行くと「痛み止め」が処方され、「痛い」原因の器官は切り離す。
予防は運動して食べることです。
若い頃から、安易に薬に頼よる生活をしないことです。
■ 植物インスリンが血糖値に働く 薬用ニガウリ :
カプセルで苦くない蘭山ニガウリ100%の 糖素減
■ 糖尿病の基本用語集 :
血糖値マメ辞典
■ 生活習慣からの体の不調、その基礎知識と対策 :
ホントナノ

